| それは2月に入ったばかりのあるうららかな午後のこと。
いつものように執務室に書類を届けに行った私に、ルヴァ様が突然こんなことを言った。
「アンジェリーク。来週の木の曜日なんですけど、執務が終わってから会えませんか?」
「・・・・木の曜日、ですか?」
「ええ、木の曜日。」ルヴァ様はにっこり笑って繰り返した。「他の予定があっても、できれば断って欲しいんです。」
「特に予定はない・・・ですけど・・・・」
いつになく強引なその口調に、ちょっぴりビックリしながらうなずくと
「そうですか・・・良かった。じゃあ、執務が終わったら補佐官室に迎えに行きますね。」
ルヴァ様は嬉しそうにまた、にっこりと微笑んだ。
執務室を出てからも、私は何だかキツネにつままれたような気分だった。
木の曜日に予定なんかあるわけない。
だってその日はバレンタイン・デー。誘われなくったって自分からルヴァ様に会いに行ってチョコレートを渡すつもりでいたんだから・・・・。
お互いに気持ちを伝え合って、晴れてコイビト同士になってから、これが初めてのバレンタイン・デー。
めいっぱい気合の入った手作りチョコレートをプレゼントするつもりで、実はもう準備を始めてた。
突然チョコレートをプレゼントされてビックリしてるルヴァ様に、その意味を教えてあげたなら・・・・・
(きっと真っ赤になって照れて・・・でもスゴク喜んでくれるんだろうな・・・・・)
普段は落ち着き払っている年上の彼の「ソノ時」の反応を想像しては、ドキドキしながら準備を進めてきた私だった。
だけど・・・・・・・
木の曜日のデートをルヴァ様の方から言い出されたことが私にはちょっぴり意外だった。
まさかルヴァ様がバレンタインデーを知っているとは思えない。主星以外ではほとんど知られてない行事だし、ルヴァ様は確かに物知りだけど、こういう世俗的なことにはからっきし弱いし・・・・。
偶然にしても、平日に誘われるのはめったにないことだった。
それにあの、いつになく強引な口調・・・・真剣な表情・・・・・。
――― まっ、いっか・・・・・。
結局私は、いつもの一言でこの問題を片付けることにした。
何はともあれ14日のルヴァ様の予定は確保できたわけだし、・・・・それに悩んでるどころじゃないのだ!
この書類をさっさと片付けて今日こそ帰りに足りない材料を買いに行かないと・・・・。試作品も作らなきゃ、ラッピングもまだ決まってないし・・・・・。
「タイヘン!もうこんな時間っ?」
私はすばやく辺りを見回して人が(ジュリアス様が)いないのを確認すると、ドレスのすそをつまみ上げ駆け足になった。
そう、素敵なバレンタインデーのために、今週は頑張らなきゃいけないのだ!
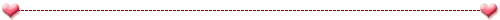
木の曜日。執務時間が終わる6時ぴったりにルヴァ様は補佐官室に姿を現した。
行き先も教えてもらえないまま待たせてあった馬車に乗せられたかと思うと、馬車はすぐに見慣れた道筋を走り始めた。
そして、二十分ばかり走ったかと思うと・・・・馬車は私にとっては既におなじみのルヴァ様の私邸の前でピタリと停車した。
「さぁ、どうぞ・・・着きましたよ。」
ルヴァ様はそう言って馬車を降りると、自分で懐から鍵束を出して玄関のドアを開けた。
そう言えば、いつもなら馬車がついたとたんに、わらわらと迎えの人が現れるのに、今日は玄関前もシンとしている・・・・。
「あの・・・・ どなたもいらっしゃらないんですか?」
恐る恐る聞く私に、ルヴァ様はまたもやにっこり笑って答えた。
「ええ。誰もいませんよ。今日はみんなお休みにしちゃいました。」
「えっ?どっ・・どうして?」
「いいじゃないですかー、別に・・・。私がいるんですから・・・。」
ね?・・・・と笑いかけると、ルヴァ様は先にたってスタスタと家の中へと入っていってしまった。
「座っててくださいね。お腹が空いたでしょう?今、お茶を入れますから・・・それですぐ食事にしましょうね?」
「食事って、あの、ルヴァ様・・・・?」
「いいから、あなたはここに座っていてくださいねー。」
私を無理やり食堂のテーブルに座らせると、ルヴァ様はそそくさと扉の向うに消えて行き・・・・・
やがて、ほどなく、ガラガラとワゴンの音をさせて戻ってきた。
ワゴンの上で湯気を立てているお皿は、オニオンスープ、テリーヌにゆで野菜のサラダ、ショートパスタと、魚のムニエル、ソースを添えた蒸し鶏とローストビーフ・・・・・プリンまである。ルヴァ様は手伝おうとする私を押しとめて、お料理をテキパキとテーブルの上に並べた。
「さぁどうぞ・・・たくさん食べてくださいねー。」
「は・・・はい・・・。」
私は相変わらずキツネにつままれたような気分のまま、勧められてナイフとフォークを動かし始めた。
「・・・・・・・・・・・・・・?」
食べ始めてすぐに、私は異変に気がついた。
ルヴァ様の私邸で食事をご馳走になることはしょっちゅうだったけど、その味付けは明らかにいつものお料理と違ってた。ちょっとしょっぱかったり、味が薄かったり、野菜が固かったり煮すぎてたり、・・・味は決して悪くないし形はカンペキなんだけど妙に素人っぽいというか・・・・何だかどれもこれも「レシピ本に書かれている通りに作りました!」みたいなお料理だった。
「・・・・どうですか?」
やや不安そうに尋ねられて、私は神妙にうなずいた。
「はい。おいしいです。」
そう。決して悪くない。どちらかと言えば、好きな味付けだった。
確かにいつもの方が美味しいのかもしれないけど、今日のはカンペキ過ぎないところが逆に親しみが持てるというか、何だか落ち着いて気楽に食べられるような気がした。
「あー、そうですか・・・良かった。」
ルヴァ様は胸に手を当てて、ほっとしたようにため息をついた。
その仕草に何だか怪しい胸騒ぎを感じて、私は恐る恐るルヴァ様にたずねた。
「これ、・・・・・・誰が作ったんですか?」
「私、ですよ。」 やや得意そうな笑顔で、ルヴァ様が答えるのを聞いて
「えええ?るっ・・ルヴァ様がっ?」
私は飛び上がらんばかりに驚いていた。
―――なっ・・・なんで?どうしていきなりルヴァ様がお料理なんか????
「ええ。すみませんねー、夕べと今朝で準備したんで、温めなおしただけのものがほとんどなんですけどねー。」
「でっ・・でも、どうしてですか?・・・・急に」
「私からのプレゼントですよ。今日、バレンタイン・デーでしょう?」
「ルヴァ様?・・・・・ご存知だったんですか?」
眼を丸くしている私にルヴァ様はもう一度にっこりと微笑んだ。
「年末にあなた私にクリスマスの話をしてくれましたよね。すごく楽しそうな顔をして・・・・。それで私も、主星の行事をいろいろ調べてみたんですよ。クリスマスは間に合いませんでしたけど、今年からはいろんなことをあなたと一緒にお祝いできたらいいと思って・・・・。」
「そうだったんですか・・・・。」
私はちょっぴりジンときていた。私を喜ばせようとして調べてくれたんだ・・・・・。忙しい執務の中で、私なんかのためにそんなことまで・・・・。
「あなたの出身の地域では『女性が告白する日』ということになっていますが、元々は恋人同士の日なんだそうです。地域によっては女性からだけじゃなくて二人で贈り物を交換し合うところもあるんだそうですよ。それを聞いて、私もやってみようかと思ったんですよ。」
「あっ・・・・プレゼント!」
贈り物を交換、と言われて私はやっと自分のチョコレートのことを思い出した。
あんまりビックリすることが立て続けに起こったもので、あやうく今日の本来の目的をすっかり忘れるところだった。
「ルヴァ様・・・・これ、受け取っていただけますか?」
チョコレートの包みを受け取ると、ルヴァ様はしばらく無言のまま、大事そうに手の中の包みに視線を落としていた。
「・・・・・開けていいですか?」
私がうなずくと、ルヴァ様はゆっくりと包みを解き始めた。
中から出てきた色とりどりのチョコレートは、準備期間も入れるとかれこれ1カ月がかりでルヴァ様のために用意したものだった。
初めて大好きになった人に、ありったけの心を込めてつくったプレゼント・・・・私は祈るような気持ちで、ルヴァ様の顔をみつめていた。
チョコレートに視線を落としたまま、ルヴァ様はとても嬉しそうな表情でひとつため息をついた。
「ああ・・・やっぱりあなたには敵いませんね?有難う、アンジェリーク。とても嬉しいですよ。」
「そんな・・・・私のほうこそ・・・・・」
ルヴァ様をビックリさせる作戦は失敗したけれど、その声の調子からはルヴァ様の感激が伝わってくるようで、私は充分に満足していた。
幸せでぼうっとなっている私の顔を覗き込むようにして、ふいにルヴァ様がこんなことを言い出した。
「でも、・・・・どうですか?あなたほどじゃないにせよ、私も満更家のこと何にもできないわけじゃないと思ったでしょう?」
「それは・・・もちろんですよ!」
私は勢い込んで答えた。男の人で・・・しかも本で勉強しただけでこれだけ料理ができるなんて大したものだった。
「あなたの仕事が忙しくても、二人で協力すれば何とか一緒にやっていけると思いませんか?」
「もちろん!!・・・・って!・・・・・・なっ、なんのハナシですか?ルヴァ様?」
びっくりして顔を上げた私の前に、ルヴァ様の顔がずいっとアップになった。
「だってあなたこの間言ったでしょう?「補佐官の仕事が忙しくて一緒に暮らしてもちゃんと私の世話ができない」って、「仕事が落ち着くまで結婚は無理だ」って・・・。だから私も、いろいろ考えてみたんですよ。私の世話なんかどうでもいいんですよ。自分で何でもちゃんとできるようにしますから。私はただあなたがそばにいてくれさえすれば、他の事なんかどうでもいいんです。」
「ルヴァ様・・・・・」
「あなたに、・・・・・そばにいて欲しいんですよ。」
まっすぐに見つめられて、胸がきゅんと、絞られるように切なくなった。
ルヴァ様、ずるい。こんなシチュエーションでそんな風に言われたら・・・・・私・・・・。
「チョコレート、とてもおいしそうですね。一緒に食べましょうか?」
そう言ってルヴァ様が伸ばした手は、チョコの箱を素通りして私の頬を捉えた。
「えっ?・・・えええぇ?」
そのまま顔を引き寄せられる。
ルヴァ様はつまみ上げたチョコレートを、あろうことか自分の口ではなく、私の唇に押し込んだ。
舌にじわっと甘いものが触れる。呼吸する暇もなく、柔らかな感触がそれに覆いかぶさった。
滑らかな感触と痺れるような甘みが、舌の上をゆっくりと行き来する。 何度も、何度も・・・・。ゆっくりと滲むように広がってゆく。
恥ずかしくて卒倒しそう・・・・・だけど、逃げられない。
チョコレートと一緒に全身の力まで溶け出してしまったみたいだった・・・・。
崩れそうになる私の背中をしっかりと腕で支えながら、耳元でささやくようにルヴァ様が言った。
「明日、二人分の休暇届を出しておきました。今夜はゆっくりしていって大丈夫ですよ。」
やられた・・・。 私は観念して目をつぶった。
ルヴァ様はどうやら本気のようだった。
この策士が本気を出したら、私なんか手もなく降参するしかないのだ。
「チョコレート、もうひとつ食べますか?」
ルヴァ様がにっこりと微笑む。私は魔法にかかったようにコクコクとうなずいた。
もうどうしようもないのだ。逆らえない。
私はそっと目を閉じて自分から唇を差し出した。
――― もう、どうとでもして・・・。
その晩、二人が食べたチョコレートは、最高に、蕩けるように、甘かった・・・・・。
-Fin-
| 
