| 「木の曜日・・・?」
「はい。来週の木の曜日です。お昼でも、お仕事が終わった後でもいいんです。ちょっとだけお目にかかれませんか?」
真っ直ぐな青い瞳に見つめられて、私はかすかに目をそらした。
危ない・・・・。こんな可憐な表情で見つめられたら、話を聞く以前にいきなり承諾してしまうではないか・・・・・・。
動悸を刻み始めた胸に何とか平常心を取り戻そうとして、私は「ごほん」とひとつ、乾いた咳払いをした。
「確約はできぬな・・・ 平日はいろいろと立て込んでいて忙しいと以前にも言ったはずだ。」
「・・・・そうですか。・・・・ごめんなさい、無理を言って・・・・・。」
しょんぼりと肩を落としたアンジェリークを見ると、立て直したつもりの気持ちがいきなりグラグラと揺らぎ始める・・・・・
思わず前言撤回しそうになる自分を心で叱り付け、私はわざと殊更に厳しい口調を繕った。
「ところでそなた、レイチェルと共に『バレンタイン・デー』とやらの祭りを企画しているそうだな・・・・・・」
「え?・・・もう・・・・?」
―――ご存知でしたか?と言いかけたアンジェリークに私はぴしゃりと決め付けた。
「あまり感心できぬな・・・・。」
「・・・・・・はあ。」
「そなた達がここにいる理由をよく考えてみるがいい。遊んでいる余裕などないはずだ。・・・・ダメだとは言わぬが、あまりハメを外さぬように。常に女王候補としての自覚を持って行動するのだ。良いな・・・・。」
「・・・・・はい。」
さびしそうに執務室を出てゆくアンジェリークの後姿を見送ると、今更ながらに「言い過ぎだったか?」と後悔の念が湧いて来る。
別に、目くじらを立てるほどのことでないというのは分かっている。女王候補の二人ともつい最近までは普通の女子高生だったのだ。
それがいきなり親元を引き離されて新宇宙の運命を担うという大きな使命と向き合わされているのだ。たまにちょっとした息抜きをするくらい、それが何だというのだ?大目に見てやれば良いではないか?・・・・・こんなイベントを企画したのも、実に彼女らしい考えではないか。決して単なるお遊びだけではないのだ。少しでも守護聖たちとコミュニケーションを取りたい、日ごろの感謝を伝えたいという素直な気持ちの表れだと言うことは、考えればすぐ分かることではないか・・・・・・。
それをどうしてあんなに突き放すような・・・・・
―――つまり・・・・・
―――会えばこうして殊更に厳しく接してしまうのは、なぜかと言うと・・・・・。
・・・・・・あの瞳で見つめられると、自分は極めて弱い。
・・・・・・最初もそうだったのだ。
健気に前向きに努力するアンジェリークに惹かれ、ひたむきな姿を愛しいと思うようになり、あの瞳に見つめられて・・・・我慢できなくなっていきなりプロポーズしてしまった。止まらなくてつい、抱擁して接吻まで奪ってしまった。
ところが彼女は少しも嫌がらず、真っ赤になりながら「わたしもジュリアス様のことがずっと好きだったんです」と打ち明けてくれたのだった。
自分の気持ちが受け入れられたことは嬉しい。心底彼女を愛しいと思っている。
本当は試験なんか落第して欲しい。こんなあちこちの男の部屋を訪ね歩くような試験など、愛くるしい彼女にはあまりにも危険すぎる。
本当ならすぐにも名乗って出たい。アンジェリークに大きく「触るでない!」と書いた札でも着けさせたいくらいなのだ・・・・。
しょんぼりと肩を落とした姿を思い出すと胸が痛んだ・・・・・。
(次の日の曜日にでも誘ってみるか・・・・・)
そう思ってスケジュール表を開いた私の視線は、次の木の曜日の日付の上でピタリと停止した。
14日・・・・・・・予定がびっしりと書き込まれたスケジュール表の木の曜日の欄には、大きなピンク色のハート・マークが書き込まれていた。昨日オリヴィエが来たときに、「今月の14日はバレンタイン・デーって言って、女の子が好きな男性にプレゼントを贈る日なんだってさ。女王候補達が何かたくらんでるらしいよ〜☆」とおちゃらけながら勝手に書きこんでいったのだ。
「・・・・・・・木の曜日・・・・・・・。」
私はスケジュール表に視線を落としたまま、呻くようにつぶやいた。
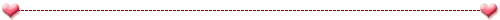
そして、木の曜日。
私がいつもどおり定例会議の会場に向かう廊下を歩いていると・・・・・・
「あっ!ジュリアス様〜!」
廊下の向こう側から、レイチェルが大声で私を呼びながら走ってきた。
「どうしたのだ、騒がしく・・・。廊下を走るなど、はしたないとは思わぬか?ここは競技場ではないのだぞ。」
「もー、固いことばかり言うんだから・・・ハイ、これ」
「む?」
「チョコレート!ワタシの愛がい〜っぱい詰まってるから、食べてネ!」
「これ、レイチェル、その言葉遣いは・・・・」
説教を聞くでもなく、礼を言わせる隙もなく、つむじ風のようにレイチェルは走り去って行った。
「・・・・・・・・・・・・。」
渡されたつつみを部屋に持ち帰っている時間はない。
私はあきらめて、包みを小脇に抱えたまま会議室の扉を開いた。
・・・・・・・・すると・・・・・・・。
そこは何やらえらい騒ぎになっていた。
いつもは遅れてくる連中までもが、どうしたことか今日は一人の遅刻者も無くずらりと顔をそろえていた。
それが皆が皆、手に二つずつの包みを抱えて、中にはこれ見よがしに包みを解いて中身をみせびらかしている者までいる。
それぞれ自分がもらった贈り物のことを声高に自慢しているのだ。会話の端々に聞こえる「アンジェリークが・・・」「レイチェルが・・・」「バレンタインが・・・」という断片的なコトバから、状況は容易に推察できた。
つまり、・・・・ここにいる全員、もらったのだ。アンジェリークとレイチェルから、「バレンタイン・デー」のプレゼントを・・・・・・。
「騒がしい!・・・静かにせぬかッ!」
私の一喝で、議場は水を打ったように静まり返った。
会議が始まり、書記官が議題を読み上げても、私の頭の中には議事がさっぱり入ってはこなかった。
つまり・・・・・・ もらったのか?みんな?
「バレンタイン・デー」の贈り物とは、好きな男にやるものではなかったのか?
全員好きということか?あり得るのか?そんなことが?
それでは何か?あのとき「好き」だと言った、アレもそうなのか?
あの「好き」は特別な「好き」というわけではなく「みんなと同じように好き」という、そういう意味だったのか?
なら何故あのような眼差しで私を見るのだ?他の連中のことも同じような風情で見ているということなのか?
大体なんだ?「皆と同じ」、そのレベルで抱擁や接吻を許すのか?それはふしだらというものではないのか?
それに、他の連中には全員贈り物を渡しておいて自分のところには来ないということは、「好き」は「好き」だけど他の連中ほど「好き」ではないということか・・・つまり「最低」ということなのか・・・・・?そうなのか・・・・・?そういうことなのか・・・・?
「あっ・・・あの・・・・ジュリアス・・・・・・・・?」
「なんだッ!」
間延びしたルヴァの声に思考を邪魔されて、思わず私は不機嫌に怒鳴り返した。
「ペンが・・・・・その〜・・・・・・・・・折れてますけど・・・・・(汗)」
「・・・・・む?」
慌てて手元を見やると、握り締めた真新しい羽ペンは、中央のあたりで見事に真っ二つに折れていた。
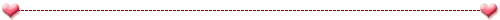
・・・・・・取りあえず、少し、待ってみよう。
執務室に戻ると、頭にもやや冷静さが戻ってきた。
光の力も充足してはいないようだし、もしかしたらこれから尋ねてくるのかもしれない・・・・・・。
今日会いたいと言っていたのだから、きっと来るに違いない。
来るだろう、必ず・・・・・。
来るに違いない・・・・・・。
・・・・・・・・・・・そう思って待っている間に、夜はとっぷりと更けていった。
「・・・・・・・・・・・・。」
私はため息をつくと、眼を通していないままの書類を束ね始めた。
冷静に考えれば来ないのが当然だった。
「忙しいから来るな」と言ったのだから、向うからは来るわけがない。
会いたければ、こちらから訪ねていくしかないのだ。
寮を訪ねれば会える。
こんな時間だ。きっと部屋にいるだろう。
こんなに気になるくらいなら、いっそ訪ねて行けばいい。
・・・・・・・・・だが、それもまずかった。
この間、日の曜日に彼女に部屋に誘われたときに「そなたの部屋にか?・・・・それはあまり感心できぬな」と断ってしまったのだ。
本当はものすごく行きたかった。彼女の寮での暮らしぶりを知りたかったし、部屋で寛いている彼女の姿はどんなにか可愛らしかろう・・・・それも見たかった。それに何より、部屋では「二人きり」になれるのだ。
二人きり。・・・だが、それが問題だった。
自分の執務室でほんの束の間二人きりになった時でさえ、我慢できずに接吻してしまったのだ。
「二人っきり」が約束された空間に入ったらどうなってしまうのだ?・・・・・いやいやいや、それはまずい。それだけは絶対避けねばならない。
しかも彼女が「自分の部屋に守護聖を招く」というこの事実、これはどうにも許しがたい。
自制心と忍耐に優れた自分でさえ我慢できなかったのだ。他の連中が我慢などできるわけがないではないか。あんなに人を信じきって、無防備でいるようでは、彼女の貞操が危ぶまれた。
あまりに心配だったので、クギを刺すつもりもあって少し強く言い過ぎてしまったのだ。
あれだけ言っておいて、自分から訪ねていくというのはあまりにも筋が通らない気がする・・・・・・・・。
「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・」
私は束ねた書類を一気に伏せた。
・・・・・・ つまり、自分は守護聖失格なのだ。
首座の守護聖などと言ってはいても、自分が口にするほど自制心があるわけでも忍耐に長けているわけでもない。
結局のところ、愚かな凡夫に過ぎぬのだ。
・・・・・・ ならばせめて、誠実であるべきではないだろうか?
口うるさく小言ばかり言うのは、決して彼女を責めているわけでも非難しているわけでもなく、愚かな自分を戒めているのだと、きちんと彼女に打ち明けるべきではないだろうか?
彼女の自分に対する気持ちをあれこれ推測する前に、まず自分の気持ちを率直に彼女に伝えるべきではないのか?
時間はもう11時を過ぎていた。
こんな時間に女性の部屋を訪ねるのは非常識極まりないことだろう。
しかし、時には常識よりも重要なことがあるはずだ。
たとえ部屋に入れてはもらえなくとも、玄関先でも、窓の外ででも、彼女に一言伝えるべきではないだろうか?
――――コンコン
立ち上がろうとした矢先にノックの音が聞こえ、私は思わず腰を浮かせた。
「あの・・・・・」
開いた扉から顔をのぞかせたのは、今まさに会いに行こうとしていたアンジェリークだった。
「アンジェリーク。・・・・どうしたのだ、こんな時間に?」
「・・・・・ごめんなさい。」
叱ったわけでもないのに、怯えるように首をすくめるアンジェリークを見て、私はまたツキンと心が痛んだ。
愛しいものをこんなに怯えさせ、傷つけて、それで本当に愛していると言えるのだろうか?
「どうしても今日中に渡したいものがあって、お仕事が終わるのを待ってたんですけど、・・・・いつまでたっても灯りが消えないから・・・」
「アンジェリーク・・・そなた・・・」
私は思わず窓の外を仰いだ。
表で待っていたのか?
「これ・・・・」
目の前に運ばれたエスプレッソのカップからは、コーヒーの香りの他にほんの少し甘いカカオの香りがした。
「それから、これ・・・・」
コトリと机の上に置かれた包みには、金色のリボンが巻かれていた。
リボンに挟まれた小さなカードに書かれた文字は
――― I Love You
「あの・・・他の方に見せないでくださいね。ジュリアス様のだけ手作りなんですよ。差別、って怒られちゃうから・・・・・」
いたずらっぽく笑う彼女を見ると私はもう止まらなかった。
「アンジェリーク!」
「え?・・・ジュっ・・ジュリアス様・・・?」
「愛しているッ!」
「あっ・・・あの、こっ、こここここ、ここ・・・執務室・・・・」
「よいのだッ!」
「よい、って・・・ジュリアス様!・・・あっ・・あっ・・・あああ〜っ・・・!」
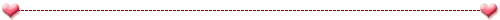
「ジュリアス様・・・お願いですから、その・・・離してください」
真っ赤になって恥らっている姿はいつにもまして可憐である。・・・私は握った手に更に力をこめた。
「どうした?・・・・・そなたは私と手をつなぐことが不快なのか?」
「そうじゃなくて、・・その・・みんな見てるし・・・恥ずかしいですぅ・・・」
日の曜日の公園は人で溢れかえっている。当然だ。人が見ているところでなければ意味がない。
「恥ずかしい?・・・そなたは私と交際することが恥ずべきことだとでも言うのか?」
「そうじゃなくて・・・」
「そうであろう。私もそなたと共にあることを誇らしく思っている。」
「いえ、そうじゃなくてジュリアス様・・・・なっ・・・何するんですかっ・・・ジュリアスさまっ!」
「愛している・・・・」
「こっ・・・公園では・・・ダメ・・・・・うっ・・・む・・・・・」
噂になるならなればよい。
いや・・・むしろ早く噂にせねばならない。
一月も経てば今度は「ホワイト・デー」とやらがやって来てしまう。
アンジェリークの「優しさ」を「好意」と勘違いする輩の魔手から彼女を守るためには、一刻も早く「アンジェリークは自分のものである」という既成事実を動かしがたいものにしておく必要があった。
「嫌なのか・・・?」
「嫌じゃなくて」
「ならよかろう?」
「あっ、ダメ!・・・んっ・・む・・・・・」
真っ赤になって身をよじっている姿は、なんとも悩ましい。
今日はこのまま、私邸に連れ帰ってしまおうか・・・・?
そうだ。それがよかろう。・・・そうしよう。
それが恋人としての、あるがままの誠実さなのだと、
あのバレンタイン・デーを経て、私はひとつ学んでいた・・・・・・・・・。
-Fin-
| 
