とにかく真っ直ぐなんだ、瞳が。
それがこの子を最初に見たときの印象。そしてその印象は今でも変わらない。
「パーティーのドレスを選んでいただけますか?」
そう言ってアンジェリークが私を訪ねてきたとき、私は正直、複雑な気持ちだった。
バレンタインデーに女王候補達を慰労するパーティーを開くことが決まった後、同僚達の間ではちょっとした騒ぎが起こった。
「誰がアンジェリークをエスコートするか?」
しばらくは、顔をあわせるたびに誰も彼も、その話題でもちきりだったんだ。
結果がどうなったかは聞いてないけど、時間的にいって、もうお相手はとっくに決まってるんだろうと思う。
好きだよ。・・・・私だって、アンジェリークのことは。
その気持ちは多分、誰にも負けてないと思う。
だけど私の気持ちは、他の連中とはちょっぴり違っているような気がしたんだ。
ずい分前、アンジェリークが育成でレイチェルに大差を付けられて負けているときから、私はなんとなくこの子が女王に選ばれるような気がしていた。
泣いても泣いても、・・・それでも逃げずに立ち上がっては突き進んでゆくこの子の強さに、いつの間にか強烈に惹かれ始めていた。
女王になれば、私たちの手の届かないところに行ってしまう・・・・その寂しさと裏腹に、どこまでも飛んでゆこうとするこの子の白い翼を、遮らずに思い切り伸ばさせてやりたい・・・そんな気持ちでずっと、見守ってきたんだ。
ところが最近、この子と来たら何だか急に綺麗になってきちゃってさ、
・・・・・多分、 恋でもしてるんじゃないか?と、そう思う。
―――それもいいんじゃないか、と私は思ってる。
世間では「女王に恋はご法度」なんて言われてるけど、この子ならもしかしてそんな前例を吹き飛ばせるかもしれない。
両方うまくやっていけるんじゃないかと、ただ漠然とそんな気がしてた。
「もちろん。お安いことだけど・・・。で、お相手は誰かな?」
そう尋ねると、アンジェリークは大きな瞳をいたずらっぽくくるっとさせて笑った。
「・・・・・言わないとダメですか?」
「ダメってこと無いけど・・・だけどヤツラがどんなカッコで来るかは大体想像がつくしね。合わせてあげられるよ?せっかくのバレンタインだもの、お揃いにしたいんじゃない?」
「・・・・・・・・・・・・。」
相変わらずニコニコと微笑んでいるその顔を見て、私は肩をすくめた。
「ヒミツ、ってわけか・・・・。」
「ダメですか?」
「・・・いいよ。問題ない。」 私は笑って答えた。
相手が分からないというのも、却っていいかもしれない。
知ってしまえば、分かっていてもちょっぴり癪にならずにはいられないだろうし・・・・・。
「任せてくれるかな?選んで後で届けてあげるから。」
そういうと、私はアンジェリークを寮に帰らせた。
本当はすぐにでも渡せたんだけれど・・・。 話しながら私の心はとっくに決まってた。
私はクローゼットいっぱいに広がる極彩色のドレスの中から真っ赤なシルク・サテンのドレスを取り上げた。
―――敢えて、赤。
あの子がオレンジやピンクの優しい色が似合うのは分かってたけど。
だけどあの子の柔らかな瞳の裏に秘められたしぶといくらいの強さに、・・・・その美しさに、いったい私たちの内の何人が気づいているんだろう。
優しさの裏に抱かれた、激しい情熱。
傷つくことが分かっているのに、歯を食いしばって立ち向かおうとするその強さ。
その強さが、愛しい・・・。
一晩だけ、あの子に私の思うがままの色を纏わせてみたかった。
強すぎる赤を抑えるように、あの子の優しさを表す白を加える。
パール・ホワイトのレースのストールと、手袋。
迷わずに一つずつ選んだ。
あの子を輝かせるためのものなら、何だってすぐ分かるような気がした・・・・・・。
何一つ、迷う余地なんかないような気がした・・・・・・。
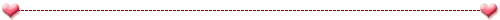
パーティー当日、私はどうにも気乗りのしない自分を叱り付け、会場へと赴いた。
私が自分のために選んだのは、これも珍しく黒だった。
あの子のことに関しては、私は脇役で構わない。
あの子が女王になるにせよ、誰かと幸せになるにせよ、その両方を掴み取るにせよ、ちゃんとその姿を見届けてあげたい。支えてあげたいと思っているから。
だけど、そうは言っても、現実はそんなにカッコイイものじゃなくて・・・・、
私は結局、あの子をエスコートしているのが誰か、見届ける勇気が無かった。
私は着くなりカードゲームの小部屋にしけこむと、いきなり大負けを連発した。
どんなに負けが込んでも、どんなに飽き飽きしても、どんなに自分を叱り飛ばしても、・・・・それでもフロアに出る気になれない自分を、私は「救いがたいな」と、心の隅で笑った。
まったく・・・・みっともないったらないね。
それでもいいカンジに時間が経って、カード部屋がお開きになると、私はフロアに寄らずにまっすぐにテラスに出た。
ここでしばらく時間をつぶして、それで帰ってしまえば苦行は終わりのはずだった。
彼女のお相手が誰か・・・先延ばしにしたっていずれは分かってしまうことだけれど、できればもうちょっと心の準備に時間が欲しかった。
―――「オリヴィエ様・・・・」

