| 出会いは2月も半ばの頃、木枯らしの吹く寒い日やった。
金髪の髪の毛に赤いリボンをちょこんと結んだその子は、友達の腕を引っ張るようにして店の中に入ってきた。
「わぁ、見て!ロザリア!すごい〜。可愛いものがいっぱいあるぅ〜!!」
「ちょっとアンジェリーク、いい加減になさったら?自由時間はほとんどないのよ。お買い物だったら帰ってからでもできるでしょう?」
「だってぇ、こんな可愛いのは売ってないもん・・・。」
「仕方ないわね・・・向かいの本屋におりますわ。あなたのくだらない買い物が終わったら迎えにきてくださる?」
青い髪の美少女が店を出てゆくと、赤いリボンの女の子は嬉しそうな笑顔で店の品をあれこれと本格的に物色し始めた。
「うわっ!これ、可愛い〜!」
「綺麗な色〜!すてきっ!」
「すご〜い、すごい、コレ!不思議〜!どうなってるのっ??」
華やかに感嘆符を連発していた少女は、カウンターの俺と眼が合った瞬間、慌てたように両手で口元を押さえた。
「ごっ、ごめんなさい・・・私、・・・うるさかったですよね?」
俺は思わず笑顔になった。
「ええよ。ゆっくり見てって・・・好きなだけ、楽しんでってや。」
「ありがとうございますっ!!」
嬉しそうにぴょこんと頭を下げると、少女は再び商品の並んだ棚を歓声をあげながら物色し始めた。
商売人やもん、嬉しそうに買い物しとる人見るの、嫌いなわけがない。
そやけど、そん中でも彼女の反応はピカ一やった。
特に力入れて仕入れた商品を「可愛い〜!」「素敵〜!」「すごい〜!」と立て続けに褒めちぎられると、なんか見てるこっちまで、背筋がゾクゾクしてきそうなくらい嬉しくなってきた。
手にも取られんで素通りされた商品見ると、「あかんな〜、・・・やっぱ値段抑えようと中途半端なトコで手ぇ打ったンがまずかったかなぁ・・・・」と妙な反省まで沸いてきた。
「あぁっ!これ!ロザリアにピッタリ〜!カワイイ!・・・・・ これ!これにします!これください!」
少女が選んだんは、最近辺境の星から仕入れたばかりの、手作りの髪飾りやった。もちろん店の自慢の品で、俺は「やっぱりな」と、心の中でうなずいた。
財布から小さなハートのかけらを出した少女を見て、俺は思わず首をかしげた。
「あんたのは?」
「・・・・・え?」
「あんた、自分のはええの?」
あんなに大騒ぎして品物選んどったくせに、その子は友達の分をひとつ買っただけで、自分の分は選んでいなかった。
俺に聞かれて、少女は照れくさそうに肩をすぼめた。
「ええっと・・・ゴメンナサイ。今日、そんなにハートを持ってきてなくて・・・・」
確かに、髪飾りの代金を払った後の財布の中は、遠目から見てもほとんど空っぽに見えた。
「・・・・・じゃ、あんたのは・・・・・これでもええか?」
俺は、カウンターの引き出しをさぐると、中から同じ種類のオレンジ色の髪飾りを出した。
「えっ、・・・でっでもっ・・・私もうハートなくて・・・・・」
「ええよ。それ売りモンやなくて試作品のサンプルやから・・・」
「いいんですか・・・?」
手のひらに押し込まれた髪飾りを見下ろすと、困った顔ような少女の顔は一瞬で飛び上がりそうな笑顔に変わった。
「わぁ・・・この色、大好きなんです!有難うございます〜!」
その笑顔がまた、めっちゃ嬉しそう〜で、・・・・なんか、見てるこっちの方まで笑えてしまいそうな笑顔やった。
「あっ、そうだ・・・・・・・あの、これ・・・お礼です。」
ごそごそとコートのポケットを探っていたかと思うと、少女はポケットから赤い包み紙を掴み出して、俺に差し出した。
「ん?」
思わず受け取ってしまってからしげしげと眺めると・・・・それは、食べかけのチョコレートやった。
「ゴメンナサイ!食べかけで!・・・あの、これスッゴク美味しくて大好きなんですけど、私が住んでるとこではホトンド売ってないんです。だから買ったらちょっとずつ食べることにしてて、だから食べかけで・・・あの・・・あ・・・・・・・怒りました?」
心配そうに見上げているその顔に、俺は噴出しそうになりながら答えた。
「怒る?なんで?・・・あんたの宝モンを分けてくれたんやろ?ありがとうな。俺も大事にちょっとずついただくわ。」
えへへ、と少女は子供みたいな顔でくすぐったそうに笑った。
「あんた・・・あまり見かけへんけど、このヘンに住んどるの?」
「ええっと・・・住んでるのはちょっとそのぉ、・・・ここからは遠くてですね、それに、普段はあんまり出かけられなくて・・・・・」
ちょうどその時、入り口の扉がバタンと開いて、さっきの美少女が顔だけのぞかせて叫んだ。
「アンジェリーク、まだですの?置いていきますわよ?」
「いや〜ん、待ってロザリア!今行くからぁ!」
戸口に向かいかけて、少女はもう一度こっちを振り向くと、俺に向かってニコッと笑顔になった。
「・・・・じゃあ・・・楽しかったです!有難うございました!」
―――嵐が去った後みたいやった。
俺は手の中に残った食べかけのチョコレートを見て、また笑ってしまった。
今までぎょうさん人にプレゼントしたりされたりしてきたけど、食べかけのチョコレートとは初めてやった。
何を隠そう、「ラヴァーズ・スイート」というマークのついたそのチョコレートは、うちのウォン商会が商品化したもんやった。
もとは小さな菓子店で細々と売られていたモンを社員が見つけ出してきて、その質の良さと独自の味わいに惚れこんだ俺が「何とか商品化したい!」と口説き落として、やっと量産開始できたんが去年の今頃のことやった。
量産言うても品質無視した大量生産なんかできんから、あまり出回ってないいうのはあの子のいうとおりやった。
「ちょっとずつ・・・・か・・・」
何や、その気持ちが嬉しかった。
丁寧に包みなおされてる金紙をむいて、一粒口に運んだ俺は・・・・・・
舌が痺れるような甘味を、ゆっくりと味わった。
そしたら何や、あの子のめっちゃくちゃ嬉しそうな顔をして、幸せそ〜うにチョコレートをかじってる姿が目に浮かんできて・・・・
―――ええ子やったな。
―――もう会えんのやろな。
そんな寂しいような、不思議な気がした。
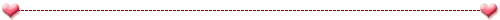
久々に家に帰ったら、大伯母様からダンボールに入った荷物が届いとった。
開けんでも中身は分かってる。ギッチリ詰まっとんのはゼンブ見合い写真や。
ようもまぁ、性懲りも無く、飽きもせず・・・・。俺はため息をつくと、その箱を前回の未開封の箱の上によっこらせっと積み上げた。
面接試験みたいに何回か会っただけで、都合の良し悪しで一生付き合う結婚相手を決めるなんて・・・・・・
俺に言わせれば「見合い」なんてモンは、えらい不可思議な、想像の範疇を超えたシステムやった。
断りきれんで仕方なく食事くらいしたこともあったけど、よそ行きの顔で来て、品定めみたいに俺のこと見る女の子、「好きになれ」言う方が無理とちゃうやろか?ヒッピーみたいなカッコして町でモノ売ってる俺でも、あの子らついてきてくれるんかな?
多分、そうやないやろな・・・・・。
そんなことを考えたとき、ふいに俺の頭ん中に、何ヶ月も前の映像が甦ってきた。
――― 一緒におるんやったら、あんな子がええな・・・・。
赤いリボンの、よく笑うあの子。
無邪気で、飾り気が無くて、やたら明るくて元気が良くて、ちょっぴりオッチョコチョイで、友達思いの優しい子。
一緒にいるだけで心の中がじんわりとあったかくなってくるような、そんな可愛い子やった。
俺はデスクの引き出しを開けると、三分の一くらいに減ったチョコレートを、少し割って口ん中に放り込んだ。
まるでアラジンのランプかマッチ売りの少女みたいに、嬉しそうなあの子の顔が浮かんできて
・・・・・・・・そして、俺はまた少し、笑ってしまった。
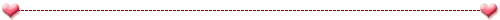
そしてまた冬が来て
俺はある日突然、「聖地」から呼び出しをくらった。
短い書状には用件も何も書いてない。「至急、出頭せよ」・・・・それだけやった。
「アホらし、・・・・テキトウに断っとけ」
お上の仕事なんか、金にはなってもオモシロイわけがない。
言い捨てた俺のコトバに、社員達は驚いたようにこぞって反対した。
・・・・・結局、秘書達に寄ってたかってかき口説かれて、俺は「とにかく話だけ聞く」と言う約束で聖地の門をくぐることになったんや。
「ようこそお越しくださいましたわ。・・・ただ今陛下がお越しになります。しばらくこちらでお待ちくださいませ・・・・・」
応接室に案内してくれた補佐官さんの顔を見て、俺は何度も首をひねった。商売柄、一度見た顔は忘れん方やった。確かにどっかで見覚えのある顔やった。
「・・・・・・・!」
あの髪飾り・・・・?
補佐官さんが会釈して背を向けかけたその瞬間、俺は驚きのあまり椅子から腰を浮かせかけた。
綺麗なブルーの髪の毛を纏めているは、豪華なドレスにはちょっとばかり不似合いな、愛らしいピンクの花の髪留めだった。
間違いない・・・・ロザリアとかいう、あの子の友達や・・・・・。
せやけどなんで、あの子の友達がこんなとこおるんやろ・・・・?
――― 「女王陛下のお成りです。」
高らかな声とともに、扉が開き・・・・
入ってきたのは女王陛下その人やなく、物々しい何台もの衝立やった。
(御簾越しか・・・・、)
女王陛下が顔を見せようが見せまいが、別にかまったことやないけど、顔も見せん相手と話するいうんは気持ちのいいことやない。
俺は何や苦々しい気分になって来るんを、どうすることもできんかった。
「ご苦労様です、ウォン総裁。・・・楽になさい。」
楽になさい、・・・ときたもんや。俺は舌打ちでもしたい気分を抑えて切り出した。
「あの・・・御用はいったい何でしょうか?」
「もちろん、あなたの会社にとってはいいお話のはずです。この聖地にウォン・コーポレーションの直営店をおくことが決定されたのです。」
決定された?・・・当の本人に断りもなく、誰がいつそんなこと決めよった!
俺はマジギレしそうになる自分をぐっと抑えた。商売人は腹立てたら負け、・・・代々伝わる家訓やった。
「店なら別にウチやなくても、他のグループでも出せるんやないですか?」
せいぜい控えめに言ったつもりの俺の言葉に、
「聖地に呼ばれることを光栄だとは思わないのですか?」
何を言ってるんだ、とばかりの口調が返ってきた。
――― 光栄・・・?
「何で有り難がらなあかんのですか?」
俺はまっすぐに御簾を見返すと言った。
「俺は欲しがってる人のところに欲しいモンを届けるんが仕事です。売った相手を幸せにできれば俺らの勝ちやし、ガッカリさせたら俺らの失敗です。相手が聖地でも貧民窟でも俺にとっては同じことです。俺は物を売ってるんとちゃいます。満足を売ってるんです。冷やかしなら、やめてもらえませんか?」
「無礼ではありませんか?」
「無礼なんはあんたらの方やないですか?あんたら本当に欲しいモンがあるんですか?ウチのブランドが欲しいだけなんやないですか?顔も見せん、よう目的も話さへん、俺の話も意見も聞かんで、それでお互いに信用して商売なんかできますか?」
「・・・・女王陛下に反抗するおつもりですか?」
俺は椅子から立ち上がった。
大人気ない言われるかも知れんけど、これだけはどうにも譲れんとこやった。
これを無くしたら、俺は俺で無くなる。
誰でも売れるモン売るんやったら、俺が売る意味がどこにある?
「失礼します。俺も忙しいんで。俺らの品物を待っててくれてる人たちがぎょうさんおるんです。その人たちを粗末にして金のあるとこだけ大事にするようになったら、俺・・・何のために商売しとんのか分からんやないですか。」
背中を向けたその瞬間―――空気を震わせるように、澄んだ声が聞こえてきた。
「待って!!!!」
「陛下!いけません!」
「だって・・・。いくら「しきたり」だからって、こんなのダメよ!こんなのやっぱりシツレイよ!」
「なりません!女王陛下が直接下々のものとお言葉を交わされるなど・・・・」
「だって、あなたさっきから私が言ってること、ゼンゼン彼に伝えてくれてないじゃない・・・・!」
「陛下っ!」
「ねぇ!・・・・・待って!」
御簾の端っこからニョキっと突き出された金髪の頭を見て、俺は一瞬フリーズした。
「・・・・・・・あ!」
金髪の少女も、俺を見ると人差し指を突き出したまんま、あんぐりと口を開けた。
「・・・・・・・あ!」
先に気を取り直したんは、彼女の方やった。
彼女はにっこりと微笑むと、御簾の影から飛び出して俺の方にまっすぐに歩み寄ってきた。
「あの・・・・私、チョコレートが欲しいんです。」
「・・・・・チョコレート?」
「『ラヴァーズ・スイート』のチョコレート、扱ってるのはウォン・コーポレーションさんだけだって聞いて・・・・・私会いに行こうと思ったんですけど、ここを出ちゃダメだって言われて・・・。わざわざ来てもらったのに失礼な事ばかりしちゃって・・・・・本当にごめんなさいっ!」
ぴょこりと下げられたその金髪の頭に金色の王冠が載っているのを見て、俺は柄にもなく動揺して両手を振った。
「いや・・・・・その・・・。」
「聖地でバレンタインデーをやりたいんです!」
下げていた頭をがばっとあげたかと思うと、少女はいきなり食らいつくような真剣な表情で俺の顔を見上げた。
「・・・・・・バレンタイン・デー?」
「女の子が好きな人に「好き」って打ち明けられる日なんです。」
「・・・ああ・・・・・・・。」
そう言えば、聞いたことのある名前やった。毎年ある時期になるとチョコレートがバカ売れする地域があるんは、俺も商売柄知っとった。
「女の子が告白するのって、すっごく勇気がいると思うんです。振り向いてもらえなかったら・・・それよりも、嫌われちゃったらどうしよう、って。・・・だけど、その日はチョコレートをあげれば、それで『好き』ってことになるんです。どうしても言えなくても、チョコレートが代わりに言ってくれるんです。」
「・・・・はぁ」
「すっごく気持ちを込めて、・・・・・『大好き』って気持ちをこめてチョコレートを贈るんです。遠くにいて会えない人だって、チョコレートを贈れば、ちょっぴりでも気持ちが届くでしょう?・・・・・そういうのもらったら、その・・・・・・・もらった人だって、ちょっとは嬉しくないですか?」
「・・・・・・・めっちゃ、嬉しいと思う・・・・・・」
俺はなぜか、咄嗟に頭ン中に食べかけのチョコレートを思い浮かべながら答えた。
「・・・・そうでしょう?」
にっこりと、少女が笑った。
「ウォンさん、・・・・・命令じゃなくて、お願いです。この聖地にあなたの会社の直営店を出して、そこでチョコレートを売ってもらえませんか?・・・・・・・ついでに私にも・・・あのチョコレート、売ってもらえますか?」
「陛下・・・・・」
「アンジェリークです。」
女王陛下は、自分を指差して、大真面目な表情のまま名乗った。
「あの・・・女王だから先に、とか言いませんから。みんなが買った後でいいんです。1個だけでもいいんです。ただ、ちょっと・・・どうしても。ちゃんと1個まるごと、プレゼントしてあげたい人がいて・・・・・・・・・・その・・・・・・。
ダメですか?ウォンさん?」
「・・・・・チャーリー、でええよ。」
俺も負けないくらい真面目な顔で名乗った。
「あ・・・・その・・・・、チャーリーさん?」
じっと見上げてる必死な表情に、俺はゆっくりとうなずき返した。
そこにおるんは、女王陛下でもなんでもない。紛れもない俺の大事なお客さんやった。
それも、俺の商品を待っててくれることにおいては、ピカ一の、特大級の大得意さんに間違いない・・・・。
「承知しました。バレンタインだけやない、ホワイトデーもまとめてお引き受けいたします。」
「きゃあ〜!」
少女は両手をあげてバンザイしたかと思うと、
「有難う!チャーリーさん!・・・・そうだ、お礼に・・・・」
そう言ってパタパタと、いきなり御簾の影に駆け込んでいった。
戻ってきた彼女のその手のひらに、しっかりと握られた食べかけのチョコレートを見て、
―――俺は、思わず微笑んだ。
-Fin-
| 
